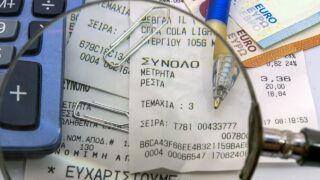フリーランスとして働いていると、毎年やってくる確定申告の時期が不安…という方も多いのではないでしょうか。
会社員と比べると税金や社会保険料の負担が大きく、「節税を知らないだけで年間数十万円以上損をする」こともあります。
この記事では、フリーランスが実践できる節税対策を網羅的にまとめました。
税金の仕組みから具体的な控除制度、注意点まで解説するので、ぜひ最後まで参考にしてください。
フリーランスが節税を考えるべき理由
フリーランスは自分で確定申告を行い、所得に応じた税金や社会保険料を納めます。主な負担は以下の通りです。
- 所得税:累進課税(稼ぐほど税率が上がる)
- 住民税:所得の約10%
- 国民健康保険:前年の所得に応じて計算
- 国民年金:定額(月約17,000円前後)
- 消費税(売上1,000万円以上で課税事業者)
所得税の税率についてはこちらです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
消費税については、資本金1,000万円未満であれば、2年間消費税が免除と認識している方もいると思いますが、正しくは、フリーランスは1月1日から6月30日の期間で、売上額が1,000万円以下の場合は、2期目も免税の対象となります。
つまり大体のフリーランスは、2期目も消費税は免税となります。
半年で売上額が1,000万円を超える個人事業主は、法人化を検討するのもいいかもしれません。
例えば、年間500万円稼いでいるフリーランスの場合、経費や控除をしっかり活用しなければ100万円以上が税金で消えてしまうケースも珍しくありません。
つまり、節税をするかどうかで、手元に残るお金が大きく変わるのです。
節税の基本の考え方は「3本柱」
節税というと難しく感じるかもしれませんが、基本はシンプルです。
- 経費を正しく計上する
- 控除制度をフル活用する
- 将来の備えになる制度を活用する
この3つを押さえるだけで、誰でも着実に節税効果を得られます。
フリーランスができる節税対策10選
1. 経費を正しく計上する
フリーランスの節税の基本は、仕事に必要な支出を経費として計上することです。
代表的な経費には以下があります。
- パソコン・周辺機器
- スマホ・通信費
- 家賃・光熱費(自宅兼事務所なら按分)
- 打ち合わせ時の飲食代(会議費)
- 書籍・セミナー代
2. 青色申告を活用する
フリーランスなら、必ず青色申告を選びましょう。
- 青色申告特別控除:最大65万円
- 専従者給与:家族に支払う給与を経費化できる
- 赤字の繰越控除:3年間繰り越せる
白色申告との差は非常に大きく、青色申告をしていないと大きな損です。
青色申告は、別途「青色申告承認申請書」を税務署に申請しなければなりません。
期限は開業から2ヶ月以内、すでに事業を行っている場合は、その年から適用させるには3月15日までに申請が必要です。
期限過ぎた場合は、よほどの事情でない限り、基本的に申請受理されないとは思います。
3. 小規模企業共済を利用する
フリーランスの「退職金制度」とも呼ばれる制度です。
- 掛金は月1,000円~7万円まで自由に設定可能
- 全額が所得控除の対象
- 将来は退職金や年金のように受け取れる
- 事業資金の借り入れする制度もある
全額所得控除となって7万円まで掛金設定したいと思いますが、1年未満の任意解約は掛け捨て、20年未満の任意解約は80%〜99.25%の返戻となります。
可能な限りこの制度は活用した方が節税にもなりますし、共済を活用した融資制度もありますので、資金繰りにも活用できます。
4. iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後資金を積み立てながら節税できる制度です。
- 掛金が全額所得控除
- 運用益も非課税
- 60歳以降に受け取り可能
注意点として、60歳まで引き出せないため「余裕資金」で利用するのが基本です。
原則、途中解約はありません。
iDeCoも小規模企業共済と同様です。
小規模企業共済より、掛金を担保に事業資金を借り入れすることができないので、よほどの余裕がない限りはどちらかを選んで加入することが良いかと思います。
5. 生命保険料控除・地震保険料控除
保険に加入している場合は、その保険料が控除対象になる場合があります。
- 生命保険料控除:最大12万円
- 地震保険料控除:最大5万円
節税効果は小さいですが、加入しているなら必ず申告しましょう。
6. 医療費控除・セルフメディケーション税制
- 医療費が年間10万円(収入にもよる)を超えた場合は「医療費控除」
- 一定の市販薬購入で利用できる「セルフメディケーション税制」
確定申告で忘れず申告することで税金が戻ってきます。
ただし、「セルフメディケーション税制」を受けるには、人間ドックや健康診断、インフルエンザワクチン等の予防接種など、適用を受けようとする年に「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」として一定の取組を行う必要があります。
対象となる市販薬については、薬局やドラッグストアのレシートに記載されています。
7. 開業費を経費にする
開業届を出す前の開業前に使った費用も「開業費」として経費計上できます。
- パソコン購入
- 開業準備のための打ち合わせ費用
- 広告宣伝費
- その他事業に関することで必要な経費
8. 少額減価償却資産の特例
パソコンやカメラなど、フリーランスには特にありがたい制度です。
ただし、青色申告をしている方のみ対象です。
- 10万円未満の備品 → 全額を一括で経費
- 30万円未満の備品 → 特例で一括経費(年間300万円まで)
9. 家族を雇う(青色事業専従者給与)
所得税の考え方として、原則「生計を共にする」家族への給与は経費の対象外となります。
しかし青色申告をしていると、配偶者や子供を事業に従事させることで、給与として支払い経費化できます。
青色事業専従者給与として対象となる人は下記の通りです。
- 青色申告者と生計を共にする配偶者、その他の親族
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上
- その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事している
青色事業専従者給与として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出
- 青色事業専従者に給与を支払っている
- 届出書に記載された方法かつ金額の範囲内で支払っている
白色申告でも専従者給与はありますが、控除の上限額が決まっています。
もし、配偶者が現在専業主婦などで制度を活用することを検討している場合は、まずは青色申告することをオススメします。
所得を分散できるため、世帯全体での節税につながります。
10. マイクロ法人
マイクロ法人とは、ご自身のみ、もしくは少人数の小規模会社のことです。
個人事業主とは別に法人を設立し、フリーランスと法人としての報酬と事業内容を分けることで税負担と社会保険料負担を軽減することができる方法です。
メリットとデメリットはこちらです。
メリット
- 社会保険料の最適化
- 所得分散
- 経費計上の幅が広がる
デメリット
- 設立コストがかかる
- 法人としての手続きや会計が複雑 → 税理士など専門家に依頼すべき
デメリットの設立コストについては、初回のみですので、長く続けていく上ではそこまでコスト高とはならないはずです。
下記は注意事項です。
- 個人事業主と法人の事業内容が同じで、契約や売上を自由に振り分けることは禁止(租税回避を疑われる可能性が高く、重大なペナルティとなる)
- 実態が伴わない二重構造は、「脱税」と扱われる可能性あり
マイクロ法人を設立する場合は、個人と法人で同じ事業とならないように明確に事業内容等分けましょう。
その上で、必ずどちらも事業として活動していきましょう。
僕はよく、せっかくフリーランスになったなら、複数事業をチャレンジすべきだと考えています。
1つを極めていくこともとても大事なことですが、パラレルキャリアは節税含めてフリーランスにとってメリットが大きいです。
パラレルキャリアについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

ぜひチャレンジしてみて、より良い節税対策をしていきましょう。
節税でやりがちな失敗と注意点
- 領収書を保存していない
- プライベート費用まで経費化してしまう
- 節税ばかりに気を取られ、資金繰りが苦しくなる
節税は「合法的にお金を残すこと」であり、無理な経費計上は税務調査のリスクを高めます。
まとめ
フリーランスの節税は、難しいテクニックを使う必要はありません。
- 経費を正しく計上する
- 青色申告をする
- 共済やiDeCoを活用する
まずはこの3つから取り組むだけで、年間数十万円規模の節税効果があります。
さらに効率的に管理したい方は、会計ソフトを導入するのがおすすめです。
どの会計ソフトがおすすめかはこちらの記事を参考にして、導入してみてください。